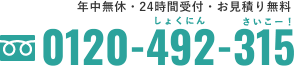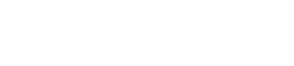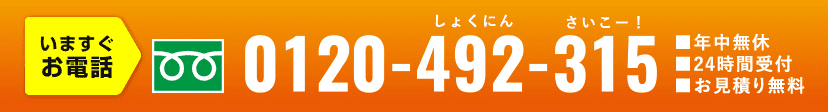水コラム
水回り
防災の日に見直す暮らしの備えと水まわりの重要性【水道職人:公式】

毎年9月1日は「防災の日」です。
日本各地で防災訓練や避難訓練が行われ、災害に備える意識を高める日として広く知られています。
自然災害が多い日本において、防災への備えは日常生活に欠かせないものです。
とくに近年では地震や豪雨、台風などによる被害が全国で発生しており、ご自宅での備えの重要性がますます高まっています。
今回は、防災の日の成り立ちや意味、ご家庭で見直すべき備え、そして水まわりとの関係性について、あらためて考えてみたいと思います。
防災の日をきっかけに、住まいの安全と暮らしの安心を見直すヒントとして、ぜひお役立てください。
目次
防災の日が制定された背景

防災の日は1960年に制定されました。
この日付には大きな意味があります。
1923年9月1日に発生した関東大震災は、死者・行方不明者合わせて10万人を超える甚大な被害をもたらしました。
首都圏を中心に広範囲で建物が倒壊し、火災も発生するなどして、大都市機能が麻痺するほどの大惨事となりました。
この未曽有の災害を教訓に、「災害への備えを忘れない日」として制定されたのが、防災の日です。
毎年この時期には、全国の自治体や学校、企業などで防災訓練や備蓄品の確認が行われ、災害への意識を高める機会となっています。
参考:2023年 関東大震災100年┃内閣府
防災の基本は自助と共助

防災において基本となるのは「自助(じじょ)」と「共助(きょうじょ)」です。
自助とは、自分やご家族の命を自分で守る力。
共助とは、地域の方々が協力して助け合う力です。
大規模災害が発生した際には、すぐに行政による救助や支援を受けられるとは限りません。
むしろ、最初の数日間は自分たちの力で身を守り、地域の方々と助け合うことが、命をつなぐ鍵となります。
そのため、ご家庭での備蓄や安否確認の手段、防災グッズの整備など、日常の中で自助力を高めておくことが重要です。
また、地域の防災訓練に参加することや、隣人とのコミュニケーションを深めることも共助の力を高める要素となります。
ご家庭で見直したい防災グッズと備蓄

防災の日を機に、まず確認したいのが非常時の備えです。
最低でも3日分、可能であれば1週間分の備蓄を目標に準備を整えておきましょう。
【備蓄しておきたい主なもの】
- 飲料水(1人あたり1日3リットルが目安)
- 保存食(缶詰やレトルト食品、アルファ米、栄養補助食品など)
- モバイルバッテリーや乾電池
- 懐中電灯
- ラジオ
- 簡易トイレやポリ袋
- ウェットティッシュやティッシュペーパー
- 常備薬や持病の薬
- お子様や高齢者向けの用品(おむつ、ミルクなど)
- ペット用の食事とトイレ用品
災害はいつ発生するかわかりません。
そのため、家族構成やライフスタイルに合わせて、必要なものを見直しながら備えておくことが大切です。
見落とされがちな水まわりの備え

防災対策というと、食料や懐中電灯などの備品に意識が向きがちですが、水まわりの備えも極めて重要です。
とくに、トイレの水洗や手洗いに使用できる水の確保ができない状況では、衛生面に深刻な影響が出る可能性があります。
災害時は断水が発生することも多く、給水が復旧するまでには数日から数週間を要する場合もあります。
そのため、水まわりの安全を守るための備えをしておくことは、感染症や二次災害を防ぐ上で重要な役割を果たします。
【水まわりに関する防災の備え】
- 飲料用と生活用に分けた水の備蓄(用途ごとにペットボトルやタンクを用意)
- 簡易トイレや凝固剤の備蓄
- 除菌用アルコール
- バケツや給水タンク(給水車利用時に必要)
- 水まわり機器の耐震対策(洗濯機の転倒防止など)
また、非常時でも使用できるように、トイレやキッチンなどの止水栓の位置と操作方法をご家族で共有しておくこともおすすめです。
災害時に注意したい水道トラブル
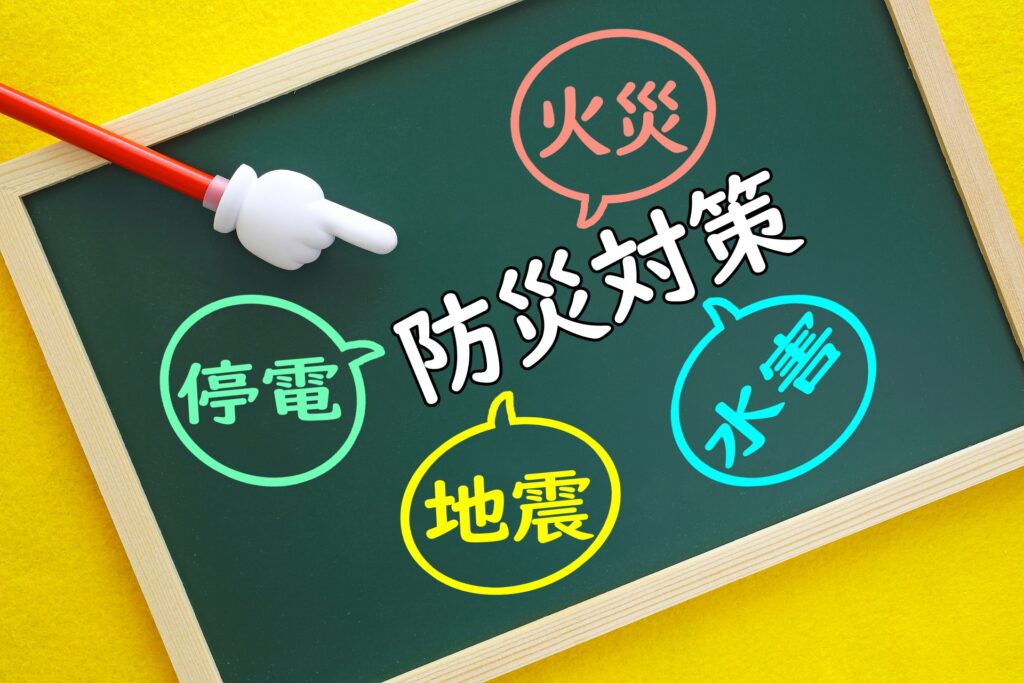
災害によって水道設備が被害を受けると、思わぬトラブルが発生することがあります。
たとえば、以下のような例が挙げられます。
- 地震により給水管が破損し、水漏れが発生する
- 凍結や高温で給湯器が破損する
- 排水管がずれて下水が逆流する
- 断水中に誤って水道を開けてしまい、復旧時に噴水のように水が漏れ出す など
このようなトラブルを未然に防ぐためには、日頃から水道設備のメンテナンスを行うとともに、非常時の対応をあらかじめ確認しておくことが求められます。
私たちやまなし水道職人では、水まわりのトラブルを防ぐための各種点検や修理に対応しており、防災の一環としての水道管理についてのアドバイスも行っています。
水まわりの点検を無料で行っているため、万が一気になる箇所がある場合は、お気軽にご相談くださいませ。
防災の日を暮らしを見直すきっかけに

防災の日は、過去の災害から学び、これからの安全を考える大切な機会です。
災害対策は、「いつか来るかもしれない」ではなく、「いつ来ても対応できるようにしておく」ことが求められます。
この機会にご家族で話し合い、防災グッズの確認や避難ルートの確認、家屋の点検など、できることから始めてみましょう。
また、水道やトイレなどの設備についても、普段からメンテナンスの意識を持つことが、万が一のときに安心につながります。
見えない場所にこそリスクが潜んでいることを忘れず、備えを怠らない姿勢が大切です。
水まわりの備えは命を守る防災行動のひとつ

災害は避けられない出来事ですが、被害を最小限にとどめるための備えは、今からでも始められます。
水まわりのトラブルは、衛生・生活機能の両面で大きな影響を及ぼします。
「水が出ない」「トイレが使えない」「排水が逆流している」といった状況では、ご家族の安全や健康が脅かされるだけではなく、心身へのストレスも増加します。
そのようなトラブルを防ぐためにも、給水設備や排水設備の点検、非常用トイレの備蓄、止水栓の確認など、水まわりに関わる防災対策を見直しておくことが重要です。
私たちやまなし水道職人では、防災対策の一環として、水まわりの安全管理に貢献しています。
どのような備えが必要なのか、ご自宅に合った対策をどう講じるべきか、お困りの際はぜひご相談ください。
安心して暮らせる住まいのために、防災の日を節目として、水まわりの備えから始めてみませんか。
最新のコラム
-
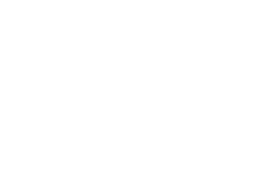
シンクつまりの原因と解消法|自分でできる対処法からプロへの依頼
キッチンのシンクがつまってしまうと、料理や片付けができなくなり日常生活に大きな支障が出ます。軽いつまりなら自分で解消できることもありますが、原因によっ…
キッチン 2025.07.31 -
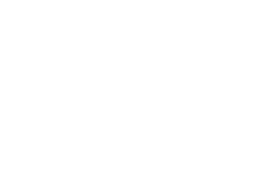
川の恵みと私たちの暮らしを見つめる「川の日」の意義と学び【水道職人:公式】
私たちの生活に欠かせない存在である川は、古くから人々の営みを支え続けてきました。 そんな生活に欠かせない川は、7月7日に「川の日」という記念日が制定さ…
その他 2025.06.30 -
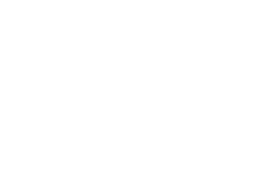
水漏れを発見したらどうする!?補修テープで今すぐできる応急処置法
キッチンや洗面所、お風呂場など、水まわりのトラブルは突然やってきます。蛇口からポタポタと水が垂れていたり、配管の接続部分から水がにじみ出ていたりしてい…
水のトラブル 2025.06.30 -
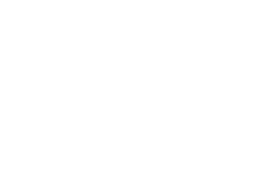
ジューンブライドの由来とその背景┃憧れの6月の花嫁に秘められたストーリー【水道職人:公式】
ジューンブライドという言葉は、日本でも広く知られるようになりました。 「6月に結婚すると幸せになれる」というこの言い伝えは、多くの女性にとって憧れのシ…
その他 2025.05.28 -
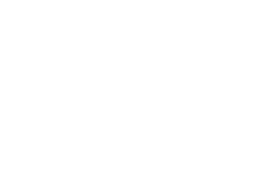
【プロが教える】配管の水漏れトラブル対策法
突然の水漏れは家庭内で最も焦るトラブルの一つです。気づいたときには床が水浸しになっていたり、壁から水が染み出していたりと、状況によっては…
水回り 2025.05.28 -
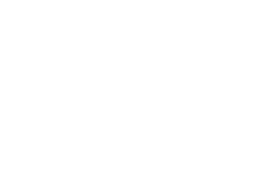
山梨県の温泉はなぜ澄んでいる?|ミネラル豊富な甲州の湯の魅力【水道職人:プロ】
富士山の麓に広がる山梨県。 透明感のある温泉が多いと言われますが、その澄み切った色合いはどこから生まれるのでしょうか。 地下深くをめぐる…
その他 2025.04.30 -
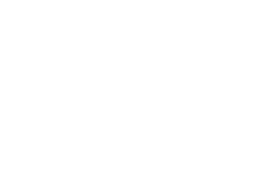
ワンプッシュ式蛇口の水が止まらない!原因と対処法を解説
洗面台やキッチンで使われるワンプッシュ式蛇口。使い勝手が良く人気の高い蛇口ですが、ある日突然水が止まらなくなってしまったり、引き棒が動かなくなったりす…
その他 2025.04.30 -
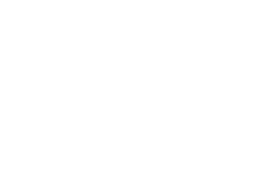
キッチン排水口のボコボコ音を解消!原因と対処法を徹底解説
「キッチンの排水口からボコボコという不気味な音がする…」このような経験をしたことはありませんか?実は、この現象は多くの家庭で起こりうる一般的な問題です…
キッチン 2025.03.28 -
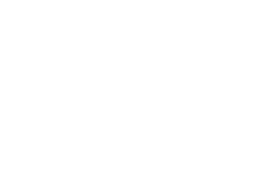
断水したけどお風呂に入るにはどうすれば良い!?代替品と浴槽の使い方【水道職人:公式】
断水での不安ごとはトイレに目が行きがちですが、お風呂に入れなくなるというトラブルも回避できません。 ずっと誰にも会わないということであれ…
水のトラブル 2025.03.06 -
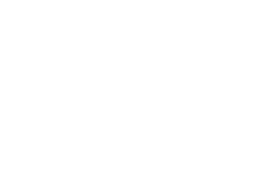
プロが教える!ユニットバスの排水口つまり予防と掃除方法
快適なバスタイムに欠かせない排水口。毎日使用するお風呂場だからこそ、定期的なお手入れが重要です。この記事では、水道のプロの視点から、ユニットバスの排水…
お風呂 2025.02.28