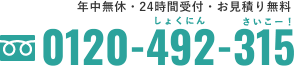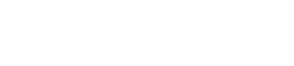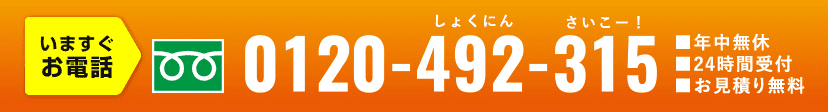水コラム
その他
山梨県の温泉はなぜ澄んでいる?|ミネラル豊富な甲州の湯の魅力【水道職人:プロ】

富士山の麓に広がる山梨県。
透明感のある温泉が多いと言われますが、その澄み切った色合いはどこから生まれるのでしょうか。
地下深くをめぐる伏流水、火山帯の熱源、断層に沿って湧き出すラドン泉。
水の経緯をたどると、甲州の温泉が持つ様々な魅力が見えてきます。
この記事では、澄んだお湯を育んだ地質について触れつつ、水から知る山梨温泉の特徴についての情報をまとめてみました。
これから山梨を訪れる方も、すでにファンだという方も、ぜひ気軽に読み進めてみてください。
目次
甲州の湯が澄んでいる理由

山梨の温泉をのぞくと、湯舟の底までくっきり見えるほど透明な湯が多いことに気づきます。
その大きな要因は二つあります。
ひとつは「富士山の伏流水」です。
富士山の裾野には厚い溶岩層が重なり、その無数のすき間が天然のフィルターの役割を果たしています。
雨や雪解け水は溶岩の中をゆっくり通り抜けるあいだに鉄分や不純物が取り除かれ、ミネラルだけをほどよく含んだ透明な地下水に生まれ変わります。
もうひとつは「深成水(しんせいすい)」と呼ばれる深い地下の温泉水です。
県西部から南部を横切る「中央構造線」という大断層を伝って、地下深くで温められた水が上昇してきます。
深成水はもともと鉄分が少なく、地表に出ても赤く濁りにくいため、そのまま澄んだ状態を保ちやすい性質があります。
このフィルターを通った富士の水とミネラル豊富な深成水が、山梨各地で混じり合いながら、透明度が高いまま湧き出すという仕組みが、甲州の湯が澄んでいる最大の理由です。
地質が育む二つの水脈

山梨県の温泉は、大きく「火山性温泉」と「深成水(しんせいすい)型温泉」に分けられます。
前者は富士火山帯の熱を受けて浅い地下で温められた伏流水が湧出するタイプ。
後者は中央構造線沿いの大断層から、地下深部で長い年月をかけて凝縮された水が上昇してくるタイプです。
それぞれ温泉として湧きだすまでのルートが異なるため、ミネラル組成や浴感にも個性が表れます。
富士火山帯がもたらす火山性温泉
山梨県の南東部は富士火山帯に属しています。
富士山や御坂山地の地下には、現在も熱を帯びた岩体(マグマの名残)が点在し、その熱が地下水を温めています。
火山性温泉は比較的浅いところで加熱されるため、湯温は高めでもミネラル分はほどよく軽やか。
河口湖温泉郷や山中湖温泉の湯が透明で肌ざわりが柔らかいのは、この浅い熱源のおかげとされています。
中央構造線沿いの深成水・ラドン泉
一方、県の西~南部を横切る「中央構造線」は、日本列島を貫く大断層です。
この断層の奥深くには高温高圧の環境があり、長い年月をかけて地下水が温められます。
こうして生まれる深成水は、カルシウムやナトリウムを豊富に含み、弱い放射線(ラドン)をわずかに帯びることがあります。
下部(しもべ)温泉や早川町の泉源が「ラジウム温泉」と呼ばれるのはそのためです。
深成水は鉄分が少なく、空気に触れても濁りにくいので、澄んだまま湯船を満たしてくれるのが特徴です。
甲府盆地を一望する絶景の湯|みたまの湯
 山梨に数ある名湯の中でも、過去に全国の温泉ファンからの投票で「絶景の温泉」として1位に輝いた温泉があります。
山梨に数ある名湯の中でも、過去に全国の温泉ファンからの投票で「絶景の温泉」として1位に輝いた温泉があります。
それが、市川三郷町の高台に湧く「みたまの湯」です。
標高およそ370メートルに位置する露天風呂からは、昼は南アルプスの稜線と甲府盆地を包む山並み、夜は宝石を散りばめたような盆地の夜景までが一望できます。
湯舟に身を沈めたまま、空と街のグラデーションをゆっくりと堪能できる贅沢なロケーションが、非常に高い支持を集める理由です。
泉質は弱アルカリ性で、肌を包むようなとろみがあり、湯上がりには指先までしっとりとした感触が残ります。
塩素臭も少なく、無色透明で飲泉も可能なやわらかなお湯は、景観の透明感とも相まって「澄んだ甲州の湯」を象徴する存在と言えますね。
甲府盆地側にせり出すように造られた湯舟に浸かって、昼と夜でまったく表情を変える景観を味わえば、山梨の温泉が持つ水と景色の調和を全身で実感できるはずです。
澄んだ温泉から知る山梨の水

富士山の天然フィルターをくぐった伏流水と、中央構造線が育む深成水。
二つの水脈が交わることで、山梨の温泉は透明感を保ちながらも、それぞれ異なる味わいを生み出しています。
湯舟の底まで見通せるクリアなお湯に身を沈めるとき、その背景にある何百年もの時をかけて生成された水のこともぜひ思い浮かべてみてください。
きっと、甲州の湯めぐりがより奥深いものになるはずです。
最新のコラム
-
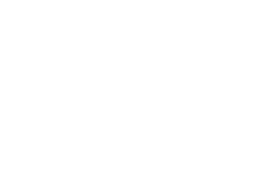
シンクつまりの原因と解消法|自分でできる対処法からプロへの依頼
キッチンのシンクがつまってしまうと、料理や片付けができなくなり日常生活に大きな支障が出ます。軽いつまりなら自分で解消できることもありますが、原因によっ…
キッチン 2025.07.31 -
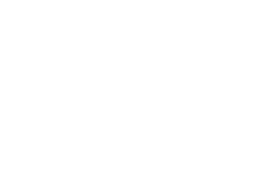
防災の日に見直す暮らしの備えと水まわりの重要性【水道職人:公式】
毎年9月1日は「防災の日」です。 日本各地で防災訓練や避難訓練が行われ、災害に備える意識を高める日として広く知られています。 自然災害が…
水回り 2025.07.31 -
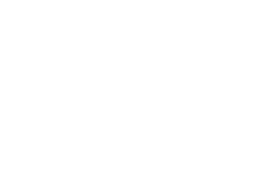
川の恵みと私たちの暮らしを見つめる「川の日」の意義と学び【水道職人:公式】
私たちの生活に欠かせない存在である川は、古くから人々の営みを支え続けてきました。 そんな生活に欠かせない川は、7月7日に「川の日」という記念日が制定さ…
その他 2025.06.30 -
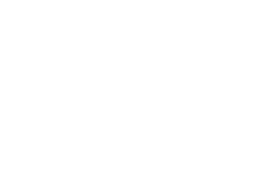
水漏れを発見したらどうする!?補修テープで今すぐできる応急処置法
キッチンや洗面所、お風呂場など、水まわりのトラブルは突然やってきます。蛇口からポタポタと水が垂れていたり、配管の接続部分から水がにじみ出ていたりしてい…
水のトラブル 2025.06.30 -
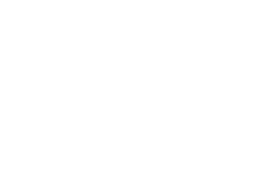
ジューンブライドの由来とその背景┃憧れの6月の花嫁に秘められたストーリー【水道職人:公式】
ジューンブライドという言葉は、日本でも広く知られるようになりました。 「6月に結婚すると幸せになれる」というこの言い伝えは、多くの女性にとって憧れのシ…
その他 2025.05.28 -
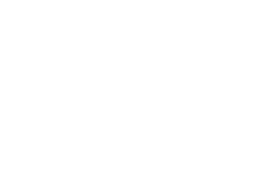
【プロが教える】配管の水漏れトラブル対策法
突然の水漏れは家庭内で最も焦るトラブルの一つです。気づいたときには床が水浸しになっていたり、壁から水が染み出していたりと、状況によっては…
水回り 2025.05.28 -
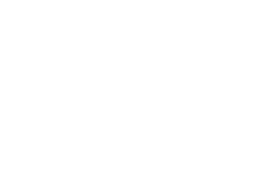
ワンプッシュ式蛇口の水が止まらない!原因と対処法を解説
洗面台やキッチンで使われるワンプッシュ式蛇口。使い勝手が良く人気の高い蛇口ですが、ある日突然水が止まらなくなってしまったり、引き棒が動かなくなったりす…
その他 2025.04.30 -
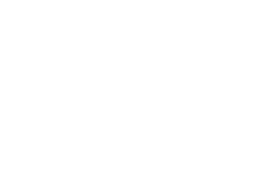
キッチン排水口のボコボコ音を解消!原因と対処法を徹底解説
「キッチンの排水口からボコボコという不気味な音がする…」このような経験をしたことはありませんか?実は、この現象は多くの家庭で起こりうる一般的な問題です…
キッチン 2025.03.28 -
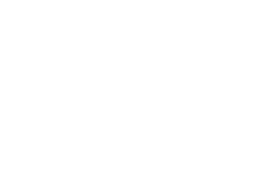
断水したけどお風呂に入るにはどうすれば良い!?代替品と浴槽の使い方【水道職人:公式】
断水での不安ごとはトイレに目が行きがちですが、お風呂に入れなくなるというトラブルも回避できません。 ずっと誰にも会わないということであれ…
水のトラブル 2025.03.06 -
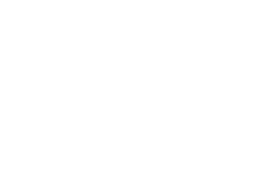
プロが教える!ユニットバスの排水口つまり予防と掃除方法
快適なバスタイムに欠かせない排水口。毎日使用するお風呂場だからこそ、定期的なお手入れが重要です。この記事では、水道のプロの視点から、ユニットバスの排水…
お風呂 2025.02.28